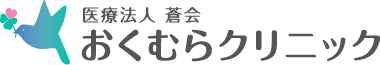精神科おくむらクリニックからの
お知らせ
-
精神障害者の自立をどう支えるか?1。精神保健福祉普及啓発研究会編。へるす出版(2006)
(2013.10.15)
1統合失調症 初発症状:理由なく休む、自宅にこもる。急性期症状:幻覚・妄想。怒りっぽくなる。 慢性期の症状:感情の反応が鈍くなる。怠けているのように見えてしまう。自宅に閉居。 治療は薬。作業療法、デイケアによって社会性と対人関係の改善を目標とする。保健所、小規模作業所、授産施設、福祉事務所...
詳細はこちらから -
(受講)CLIP講演会を聴かせて頂きました。
(2013.10.12)
ヒルトン大阪で、CLIP:Cognition LInk Project講演会を聴きました。 糖尿病などの生活習慣病やうつを治療することで、脳を守り、変性疾患として捉えてきた認知症の発症を予防できるとする報告があり、結果的に健康寿命を延ばす可能性もあるという内容でした。 認知症をアルツハイマー...
詳細はこちらから -
(文献)精神科臨床サービス(2011年1月号)。特集:アウトリーチで変わる精神科臨床サービス。
(2013.10.11)
公的精神保健福祉機関によるアウトリーチ、小川一夫、井関和俊 共著 保健所などの相談支援サービスは、地域精神保健医療の起点となる。 診療報酬や福祉サービス契約にアクセス出来ない方を支援する意義は大きい。 一次的サービスとは、基礎的な地域生活支援。 二次的サービスには、危機介入、慢性重症例へ...
詳細はこちらから -
(図書)慢性頭痛の診療ガイドライン2013、医学書院。
(2013.10.11)
片頭痛の急性期治療には、イミグランやアマージ、レルパックス、カロナール、ボルタレンがある(グレードA)。 片頭痛の予防に、デパケン、トリプタノールがグレードAで推奨されている。 緊張型頭痛の急性期治療には、カロナール、ボルタレン、ロキソニンがグレードA。 緊張型頭痛の予防に、トリプタノール...
詳細はこちらから -
地域包括支援センター様、済生会和歌山病院様のおかげで、認知症治療のよい対応が出来ました。
(2013.10.11)
ご家族→第1圏域地域包括支援センター→当院→済生会和歌山病院地域連携室→同病院放射線科→同病院脳神経外科 認知症への特別な連携システムなく、ご家族の気づき、包括支援センターの家族への説明、済生会病院内での時間外での早急な対応が出来ることは素晴ら...
詳細はこちらから -
精神障害者の自立をどう支えるか?。精神保健福祉普及啓発研究会編。へるす出版(2006)
(2013.10.09)
精神障害者の自立をどう支えるか。精神保健福祉普及啓発研究会編。へるす出版(2006) 2002年、精神障害者居宅介護等事業および精神障害者訪問介護(ホームヘルプサービス)事業等の実施。 ?しばしば生じる生活のしづらさ。 外出することに緊張が伴う。交流が苦手。身体のだるさがある。意欲がない。...
詳細はこちらから -
Expert Rev. Neurother. 13(7), 767-783, 2013
(2013.10.09)
統合失調症の治療のゴールは再発しないこと。持効性注射剤は再発を予防するというデータがある。日本以外では、リスパダール、エビリファイ、ジプレキサの持効性注射剤がある。薬代は高いが、入院した場合を考えると安い。一度注射してしまった後の副作用については、上記3剤は、ゆっくり効果が出現する機序となってい...
詳細はこちらから -
うつと体の痛みのCM。
(2013.10.08)
うつ病の64%の方がからだの痛みを感じておられます。 http://www.shionogi.co.jp/company/news/2013/qdv9fu000000ddll-att/qdv9fu000000ddns.pdf 認知症の薬物治療の厚生労働省ガイドラインでも、サインバルタが痛みへ...
詳細はこちらから -
石原千秋。「こころ」で読みなおす漱石文学。朝日新聞出版、2013。
(2013.10.08)
1914年、朝日新聞に連載された。 1960年代、こころは高校の教科書収録されうようになった。 1人の人間を死に追いやったとして、その人はそのために自分も自殺をしなければならないのでしょうか。それは真っ当な倫理観と言えるでしょうか。 先生は内側の自分が不安定であった。外側の自分を仕立てあげ...
詳細はこちらから -
自殺のない社会へ。経済学・政治学からのエビデンスに基づくアプローチ。有斐閣、2013。より
(2013.10.07)
澤田康幸、上田路子、松林哲也。自殺のない社会へ。経済学・政治学からのエビデンス基づくアプローチ。有斐閣、2013。 2006年以降の自治体による自殺予防対策は自殺の予防に一定の効果を与えた(2012年に自殺者3万人を割った)可能性がある。 高齢者の孤立が自殺のリスクを高める傾向がある。震災後...
詳細はこちらから